はじめに:変化が止まるあの違和感、あなたも感じていませんか?

まいど!週3ジムに通う会社員のおこめちゃんです!
筋トレ運動の習慣をつけて頑張っていると、とある壁にぶつかる。
それは、
「いつもどおりジムに通ってるのに、最近全然体が変わらない……」
やってるのに結果が出ない。モチベ下がりますよね。
私自身、筋トレ開始後6ヶ月をすぎた頃にその状態になり、2週間ほど筋トレを辞めてしまったことがありました。
それでも現状維持は嫌だと思い、自分なりに調べて試行錯誤してみることに。
すると、
「何にも変わってない」「頑張りが足りない」わけじゃなく、
体が「慣れ」を始めたサインであり、むしろ次のステップに行くための状態だと気付きました。
筋トレ・食事・回復という三本柱を、ちょっとだけ“進化させる”だけで、また体は応えてくれます。
ということで、この記事では過去の私と同じように、
モヤモヤしてやる気が停滞する人少しでもお役に立てれば嬉しいです!
なぜ“同じメニュー”で効かなくなるのか?
1. 刺激に体が慣れてしまう
トレーニングを続けると、体は効率的に動くように最適化されていきます。

いわゆる”慣れ”ってやつやな。
同じ負荷・回数・動作を続けると、筋肉・神経・代謝系がそれに“慣れて”しまい、以前と同じ刺激では変化を起こせなくなります。
たとえば、最初は重いと感じていたダンベルでも、しばらく使っていると「余裕」が生まれませんか?
筋力トレーニングの基礎として、強度・量・動作パターンを少しずつ上げていかないと、停滞を招きやすいです。
ですので慣れてきたと感じたら、「重量を上げる」「回数を増やす」などのアプローチを行い、
自分の限界に近いレベルでトレーニングをすることをお勧めします。
◼️挫折しないコツ
重量や回数を記録しておくのがおすすめ!
後から見返すと、自分のレベルアップの軌跡が可視化されて達成感が得られます。

いつも60kgでやってるレッグプレス、しばらくサボったら上がらず50kgでもしんどくなってた… 悲しすぎるで〜
2. 代謝が落ちて省エネモードになる
食事制限を続け体重が落ちてくると、筋肉量や基礎代謝が落ちてしまうことがあります。
体が省エネモードになるとカロリー消費を抑えようとする反応が起こるため、「がんばってる割に結果が出ない」感覚を生む大きな原因の一つ。
私は自由に食べているので代謝が落ちることはないのですが、
食事制限をされた上で代謝が落ちたと感じる方は、チートディ(好きに食べて良い日)をつくりましょう!
3. 悪い食習慣で効果が打ち消しに

人の体は食べたものでできているー
運動だけ変えても、食事があまりにも自由奔放だと成果が出づらくなります。
例えば、
- タンパク質が不足している
- 一食に偏る、あるいは一日トータルで足りていない
- 朝食を抜いていたり、夜遅く高脂質・高炭水化物をとっていたり
- 飲酒量・間食で逆にカロリー過剰になっている
などが、停滞ラインを引く要因になることも。
特にたんぱく質は筋肉維持・合成に不可欠。
総量だけでなくタイミングも必要で、1 日のたんぱく質を朝昼夜でバランスよく摂ることが、脂肪の原料と筋力UPに影響するという説もあるようです。
ちなみに厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)、18~64歳では男性65g、女性50gをタンパク質の推奨量としています。
最適なバランスは個人によって変わりますので、
自分にあった食事サイクルを見つけていきましょう( ˙˘˙ )ノ
停滞期を突破する 3 本の鍵 ― 刺激・栄養・回復
ここからは、具体的な打開策を “あなたの生活に沿う形” で。全部実行できたら理想だけど、まずひとつずつ挑戦して、体の反応を観察できるようにしよう。
鍵①:トレーニング刺激を刷新する
■トレーニングの負荷を変えてみる
トレーニング効果を持続させるために、必ず導入したい考え方が「漸進的過負荷」。
つまり、少しずつ、着実に“刺激を強める”ことです。
重さを変える、セット数を変える、休憩を変える、テンポを変える……
いろんな方法があります。
◼️負荷の調整例
・セット数と反復回数
負荷を増やす: セット数を増やす、反復回数を増やす(筋肥大)、反復回数を減らす(最大筋力)。
負荷を減らす: セット数を減らす、反復回数を減らす。
・強度(重量)
負荷を増やす: 重量を増やす。
負荷を減らす: 重量を減らす。
・テンポ(速度)
負荷を増やす: 筋肉への張力時間を増やすため、ゆっくりとしたテンポで行う。パワー向上には、軽い重量で素早い動作を行う。
負荷を減らす: 軽いテンポで行う。
・可動域
負荷を増やす: 可動域を広げる。
負荷を減らす: 可動域を狭める。
・休息時間
負荷を増やす: 休息時間を短くする。
負荷を減らす: 休息時間を長くする。
ポイントは、 毎回大きく変える のではなく、 小さな変化を積み重ねる こと。
NASM などでは「10 % ルール(週あたり 10 % 以内の負荷増加)」という指針も紹介されてるようですが、無理のない範囲でトライアンドエラーしてみましょう。
■ 種目・順序・休憩時間・組み合わせバリエーションを取り入れる
- いつもマシン中心 → 自重・フリーウエイト・ケーブル系をミックス
- スクワット → ランジ →ステップアップ →ブルガリアンスクワット など順序を入れ替える
- スーパーセット/ドロップセット/休憩ポーズ法などを導入
- セット間休憩時間を変えて、回復を制限するような変化を加える
こうした“変化”が、「体を驚かせる」刺激になりますよ♪
■ 有酸素運動との組み合わせ(筋トレ後に軽め運動を追加)
筋トレ後に軽い有酸素(20〜30 分程度)を挟むと、体が脂肪をエネルギーにしやすい環境になる、という報告も。
筋トレで刺激を与えた直後に、有酸素で“燃やす”流れを作る狙い!

わしはいつも最後にランニングで締めてるで!
スッキリできて最高に幸せになるんや〜
鍵②:食事・たんぱく質最適化
トレーニング変えても、栄養が土台にないと成果が発揮できない。ここは特に丁寧に。
■ 総タンパク質量を確保(体重 × 1.6~2.2 g が目安)
上で書いたように、たんぱく質の推奨量(18~64歳では男性65g、女性50g)を目安に、
トレーニングで筋肉量を増やしたい人は多めに取るなど調整していきましょう!
■ 分配・タイミングを整える(“均等性”の重要性)
私は、一日を通してバランスよく摂るように意識しています。
たとえば、朝・昼・夜に均等にタンパク質を振り分けることで、筋タンパク合成を維持しやすくなるという研究が「evenness of protein intake」では書かれていました。
また、女性アスリートを対象に「運動前後に体重 × 0.32〜0.38 g のタンパク質摂取」が、運動応答に好影響をもたらすという報告も。
ただし、いっぱい摂ればいいってもんでもない!と私は思っています。
一食あたり 40 g を超えるような超高量の摂取はそれ以上の効果を出すとは限らないという報告も出ているようなので、一度確認してみてください。
■ 夜遅い食事・飲酒時の工夫

毎日朝から夜まで働いていて夜ご飯の時間が遅くなる…
実は私もそんな日が多く、夜 22 時以降の食事やお酒が続くこともしばしば。。
深夜食多め&お酒大好きな私がせめて意識しているのはこちら。
- 夜食の主菜は“消化のよいたんぱく質”(魚、鶏むね、豆腐など)
- 炭水化物は量を控えめに、GI 値の低いものを選ぶ
- 脂質・揚げ物を減らす
- お酒を飲むなら、糖質オフ・適量+水分補給を意識する
- 飲酒した日の翌日はタンパク質量を少し上乗せし、回復をサポート
また、お酒はアルコール代謝優先になるため、タンパク質代謝が後ろに回るとも言われていて、飲酒の頻度と量も見直しましょう!
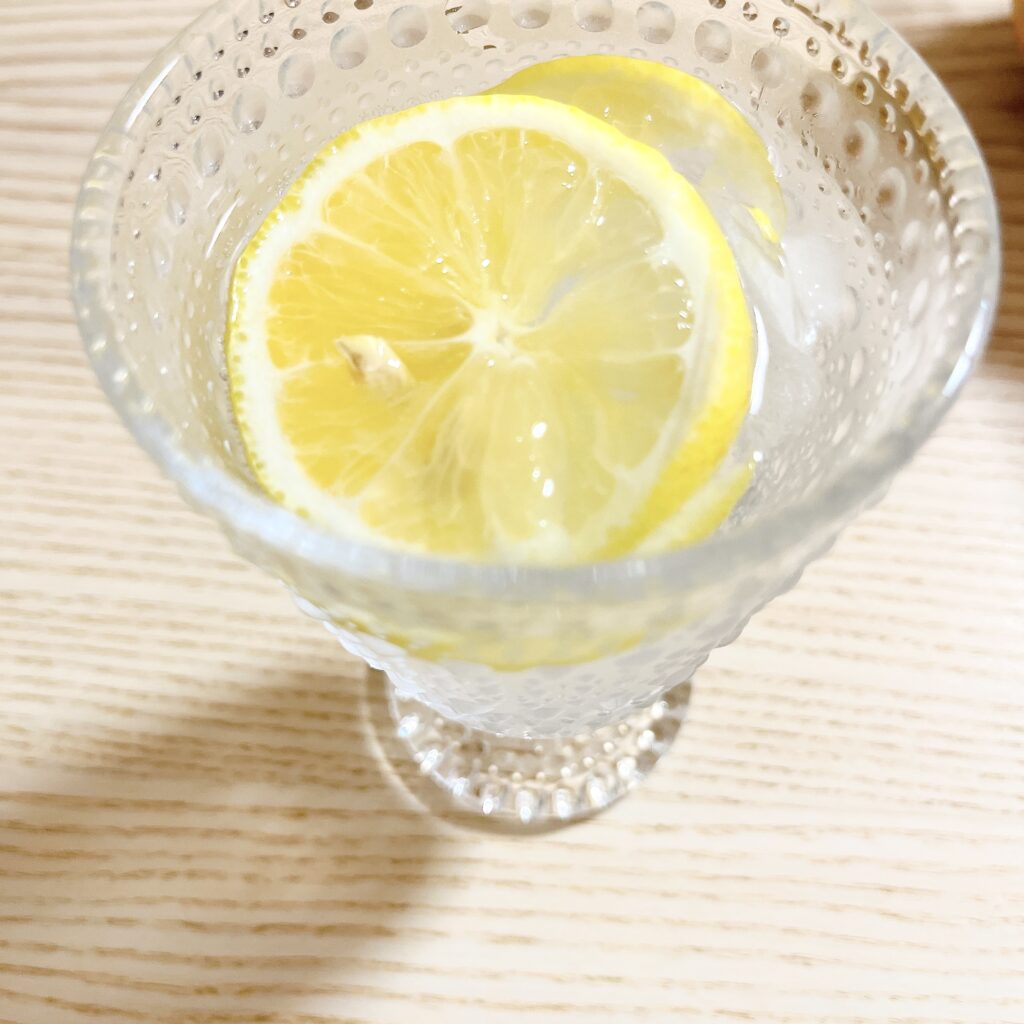
■ 間食・プロテイン補助で底上げする
日中は外にいるから、なかなか食事コントロールができない…
そういう場合は、トレーニング日の前後や空腹時間帯に、プロテインバー・プロテインドリンク・ナッツ+プロテイン混ぜなどを取り入れるようにしましょう。
私は昼休み・残業時に良くSAVASのドリンクを飲んでいます。補助的にタンパク質を底上げできる!
鍵③:回復と生活リズムの最適化
トレーニングと食事だけで突っ走ると、疲労・ストレス・回復不足に負ける。だから回復と生活リズムもセットで整えることが大事。
■ 睡眠の質と量を確保する
7~8 時間程度を目安に(個人差あり)しっかり休みましょう。
睡眠不足は成長ホルモン分泌・代謝調整・ホルモンバランスに悪影響を与え、脂肪燃焼効率を下げてしまいます。
また、寝る直前の強い光・スマホ操作・カフェイン摂取を控えると、より深い睡眠が得やすくなります。

スマートウォッチやアプリで睡眠スコアをつけるのもおすすめやで!
例えばFitbit、私の周りも良く使っています。
歩数、心拍数、睡眠の質などの健康データを自動で記録・管理すること、通知の確認やキャッシュレス決済(Suicaなど)、エクササイズ時の活動記録など
■ 整体・メンテナンスを活用する日を作る
定期的に通う整体を、ただの「メンテ」ではなく「回復促進」に使ってみてください。
筋膜リリース・可動域改善・血流促進を意図的に受けて、トレーニング日のパフォーマンス保全に生かしてみることをお勧めします。
■ NEAT(非運動性活動量)を上げる
ジム以外の時間を“自然に動かす”ようにするのも強力。通勤で歩く・階段を使う・姿勢を変える・家事動作を増やすなど、小さな運動を積み重ねると、1 日全体の消費エネルギーが底上げされるようです。
■ ストレス管理・定期的なリラックスタイム
ストレス過多はコルチゾールを上げ、脂肪蓄積・筋合成阻害を誘発する。瞑想・深呼吸・ストレッチ・軽いヨガなどで、副交感神経を優位にできる時間を作ってみてください。
毎朝10分、Youtubeでヨガをやるとスッキリいい1日が送れますよ(*´∇`*)
実践してみた「停滞期突破プラン例」
最後に、ここまでの情報を盛り込んだ 3ヶ月のプラン例を記載します!
※あくまでモデル、あなたの体調・スケジュールに合わせて柔軟に変えてださいね♪
| 期間 | 要点 | 内容 |
| Week 1–4(刺激導入期) | 刺激変化 + タンパク質底上げ | 種目ローテーション導入、テンポ変化を加える。朝にプロテイン軽食を導入。整体を回復系重点モードにする。 |
| Week 5–8(強化期) | 減量期プラス成長期 | 重量アップ/スーパーセット導入/筋トレ後有酸素追加。食事中のたんぱく質バランス強化。飲酒日を調整。 |
| Week 9–12(評価・最適化期) | 見直し + 微調整 | 食事ログで過不足確認。不足タンパク質を調整。チートディを週 1 回設けて代謝を刺激。翌サイクルに備える。 |
ポイント
・各週で「どこを何%変えるか」を計画して、「少しずつ変える」ことを意識
・過去 4 週間の体重・見た目・疲労感を振り返る時間を設ける
・結果を見ながら、プランの良かったところを強め、合わないところを修正する
この繰り返しで、「また痩せる体」「反応する体」に戻していける。
おわりに:停滞期は成長のステージ。焦らず進もう

停滞期は、あなただけが通るものでも、良くないものでもないです。
体がもう一段階変わろうと準備しているサインとして受け入れましょう(*´˘`*)
焦らず、諦めず、一緒に壁を乗り越えていきましょう!

おこめちゃん
週3ジムで毎日アップデートし続けたいアラサー会社員。
働きながらも健康的なライフスタイルと副業にチャレンジ中!
100歳でも元気に乾杯!を目指す酒飲みのブログです。
#ジム #体づくり #ライフスタイル #FP #晩酌 #料理
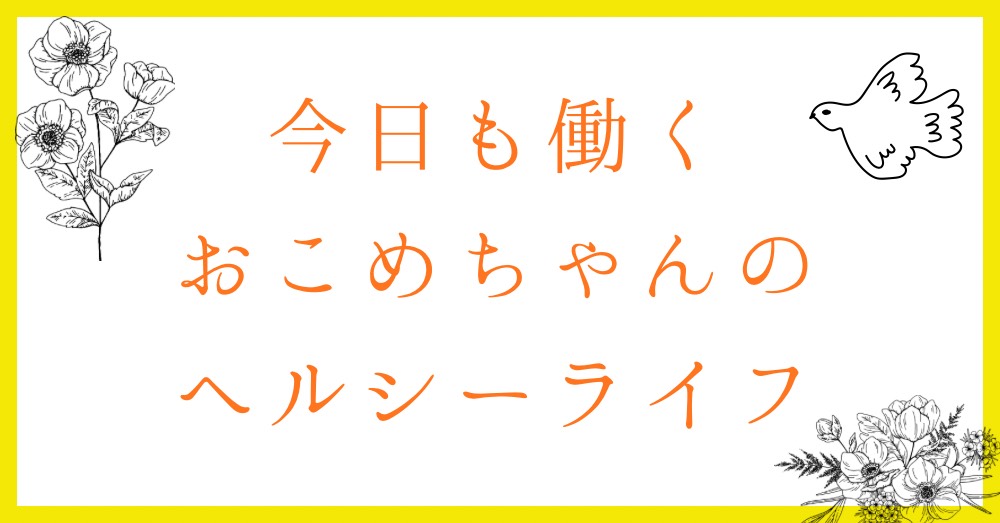
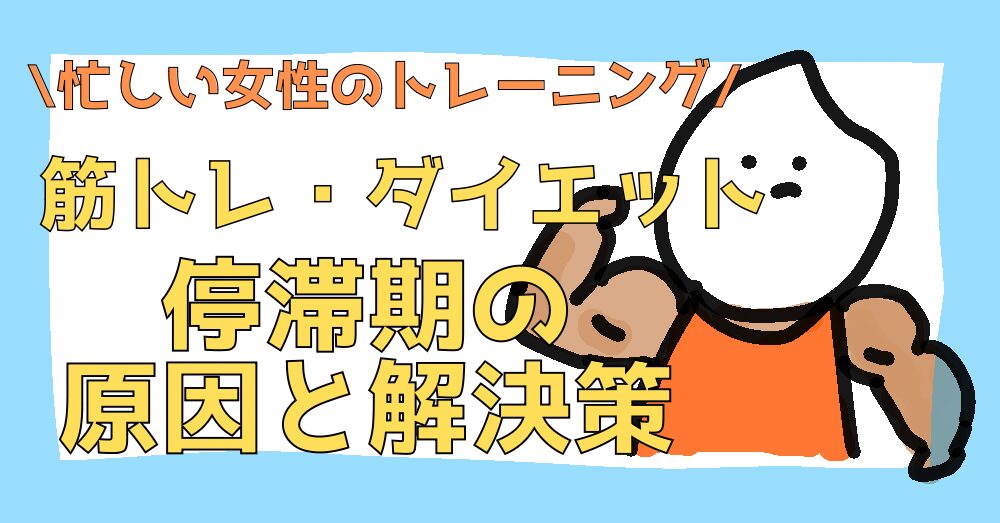
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d6adc99.4944dd9e.4d6adc9a.61ca2969/?me_id=1386156&item_id=10000108&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkosakasyoten%2Fcabinet%2Fimgrc0108796287.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d6acf5e.e9ecd3c0.4d6acf5f.70e085f0/?me_id=1429195&item_id=10000180&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkabu-fivestar%2Fcabinet%2Fcompass1760504019.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a05a8f7.f247647e.4a05a8f8.ef16c227/?me_id=1384136&item_id=10000112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flively777%2Fcabinet%2F07220892%2F10054577%2Ftop_10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント